きれいな樹形を維持するための「剪定」。「でも、どんどん成長させて大きくしたいから切るなんてもったいない……」そうお考えの方も多いのではないでしょうか?
実は剪定をする目的は樹形を整えるだけではありません。観葉植物を健やかに育てていくためにも大事な工程なのです。
今回は、観葉植物を剪定する理由と、選定する頻度や時期、選定方法、注意点などをご紹介いたします。ぜひ参考にしてみてください!
観葉植物の剪定の目的は樹形を整えるだけではない!
観葉植物の剪定にはいくつかの目的があります。大きく分けて4つご紹介します。
- 樹形を整える:伸びすぎた枝や葉を剪定することで、バランスの取れた美しい樹形を保つことができます。
- 健康維持:枯れた葉や病気になった部分を取り除くことで、病害虫の発生を防ぎ、植物の健康を維持します。
- 成長促進:古い葉や枝を取り除くことで、新しい芽が出やすくなり、植物の成長を促します。
- 風通しの改善:葉が密集しすぎると通気性が悪くなり、カビや害虫の原因になります。剪定によって風通しをよくすることが重要です。
観葉植物の適切な剪定時期は春!頻度は年に1~2回
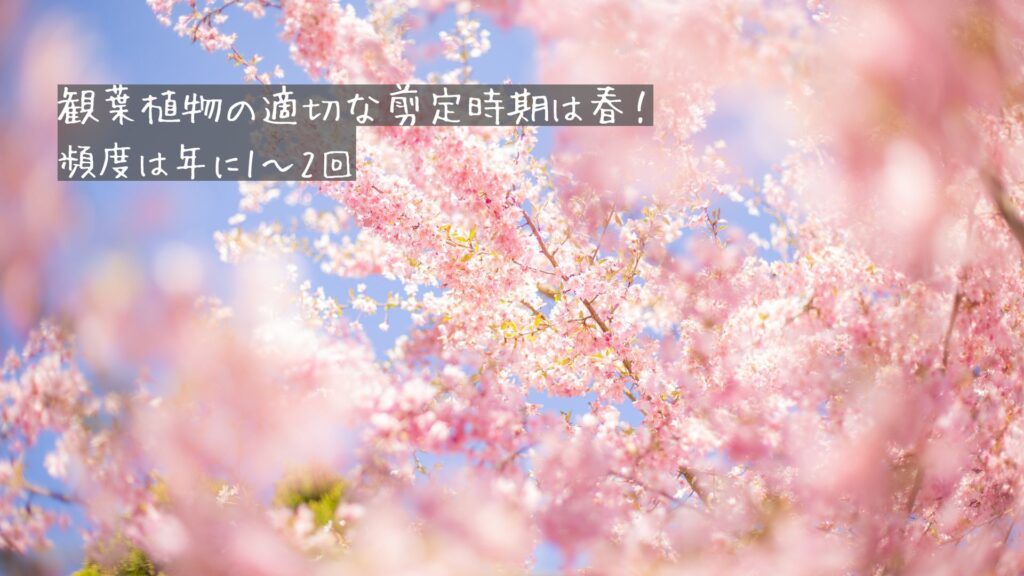
剪定は植物の種類によって適切な時期や頻度が異なります。そのため、ここでは一般的な目安をご紹介します。ご自宅の観葉植物を剪定する際は、鉢の状態を確認しながら行うようにしましょう。
- 最適な時期:春から初夏(3月下旬〜6月)が適しています。この時期は観葉植物が成長期に入るため、剪定後の回復が早く、新しい芽が出やすくなります。
- 避けるべき時期:冬の寒い時期(11月〜2月)は寒さゆえに成長が鈍るため、大幅な剪定は避けるのが無難です。
- 剪定の頻度:年に1〜2回の本格的な剪定に加え、枯れた葉や傷んだ部分はこまめに取り除くとよいでしょう。
剪定に必要なツール4つ
適切な剪定を行うためには、以下のツールを準備しておきましょう。
- 剪定ばさみ:細かい作業に適した小型のものがおすすめ。
- 消毒液:ハサミの刃を消毒することで、病気の感染を防ぐ。
- ゴム手袋:手を保護し、樹液や汚れを防ぐ。(特にウンベラータやベンガレンシスなどのフィカスの樹液はかぶれる可能性が高いので注意)
- 新聞紙やシート、ごみ袋:剪定後の後片付けを簡単にするために準備。
剪定方法の種類3つとやり方
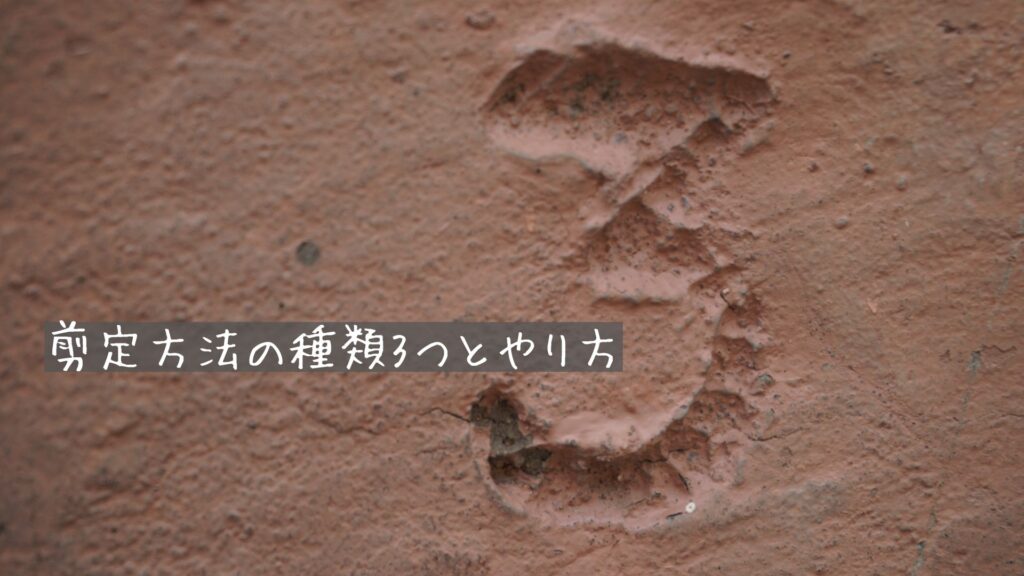
剪定の方法は主に以下の3種類に分けられます。
(1) 間引き剪定
- 目的:不要な枝葉を取り除き、風通しを良くする。
- やり方:
- 主軸となる幹を中心に内側に向かって伸びている枝を根元から切る。
- 重なり合っている葉を適度に間引く。
- 病気や害虫の被害を受けた部分は早めに除去する。
(2) 切り戻し剪定
- 目的:成長しすぎた部分をカットし、新しい芽の発生を促す。
- やり方:
- 伸びすぎた枝を適当な長さで切る。
- 葉が込み合っている部分は適度に間引く。
- カットした部分のすぐ下に新しい芽があることを確認しながら剪定する。
(3) 整形剪定
- 目的:美しい樹形を保ち、観賞価値を高める。
- やり方:
- 外観を意識しながらバランスよくカットする。
- 全体的なシルエットを整えるように調整。
- 丸みを帯びた形や、すっきりとしたデザインを意識する。
観葉植物の剪定の注意点4つ!ストレスや細菌感染に注意
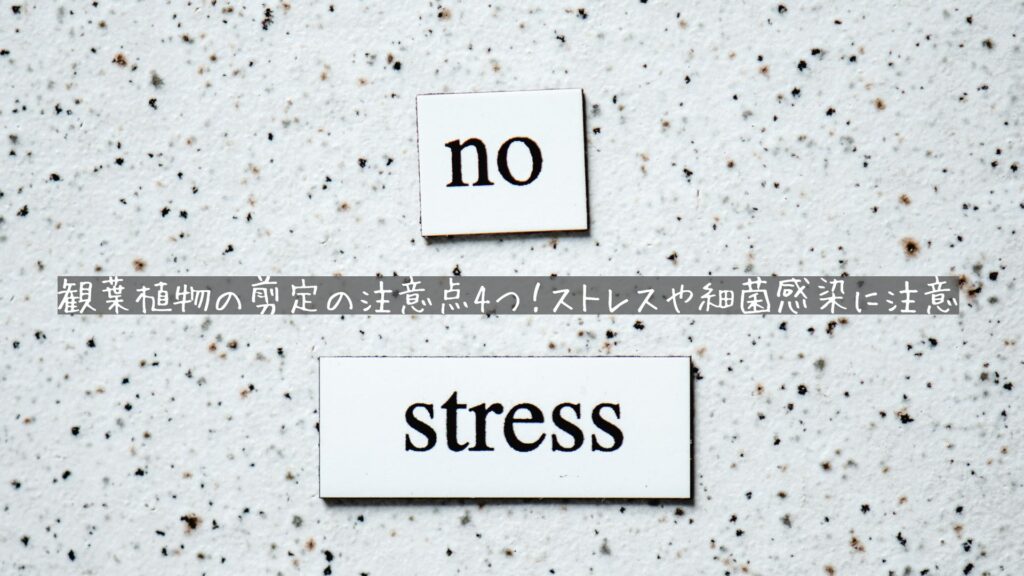
剪定を行う際には、以下の点に注意しましょう。
- 剪定後の管理:剪定後は植物がストレスを受けるため、直射日光を避け、適度な水やりを行いましょう。
- 切り口の処理:切り口が小さい場合は大丈夫な場合が多いですが、ある程度切り口が大きい場合は、剪定した部分が細菌や病気に感染しないよう、切り口に癒合剤を塗るとよいでしょう。瞬間接着剤を塗っている方もYouTubeでお見受けしたのですが、邪道なようなので、マネする場合は自己責任で!
- 種類に応じた剪定:観葉植物の種類によって適した剪定方法が異なります。例えば、ガジュマルやパキラは春先に葉っぱをすべて切ってしまうような強めな剪定にも耐えてくれる場合がありますが、シダ類は過度な剪定を避けるべきです。
- 一度に切りすぎない:植物に過度な負担をかけないよう、全体の1/3以下の範囲で剪定するのが理想的です。前項と同じく、その植物の耐性を見ながら選定してあげましょう。
まとめ
室内で育てる観葉植物の剪定は、美しい形を保ち、健康を維持するために重要な作業です。適切な時期と方法で剪定を行い、植物にとって最適な環境を整えましょう。春にしっかり剪定することで、花や実をつけてくれる植物もあるので、この時期に念入りにお手入れしてあげるのがおすすめです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
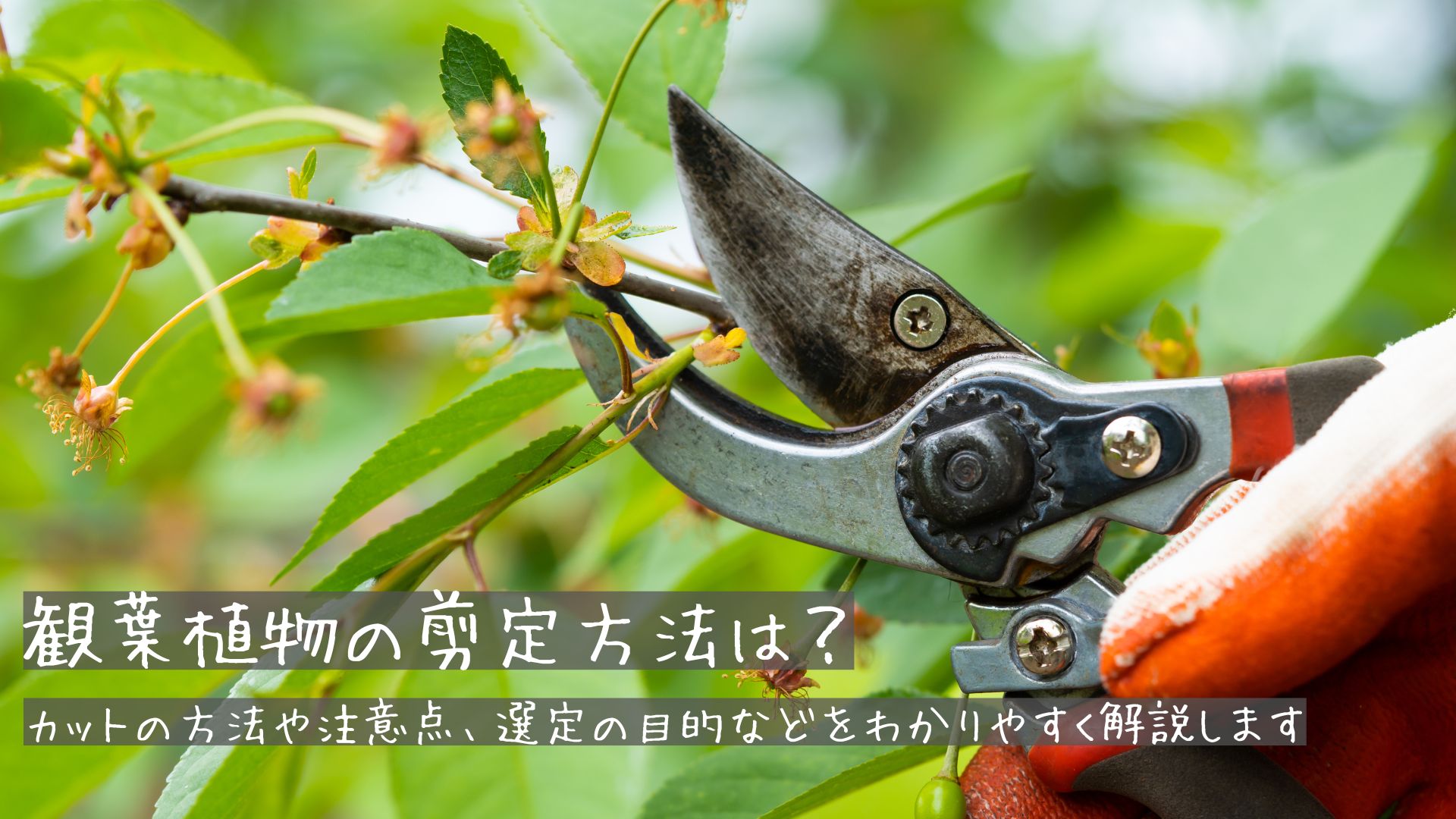



コメント